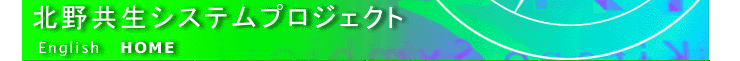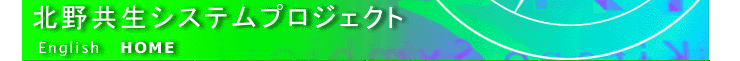システムバイオロジーとは?
システムバイオロジーは、生物をシステムとして理解することを目指した生物学の一分野です。生物をシステムレベルで理解しようという試みは、1960年代から生命科学で繰り返し挑戦されてきたテーマです。例えば、Weinerの提唱したサイバネティクスは、動物や機械を制御や通信理論の観点から記述しようという試みでした。残念ながら、その当時は分子生物学の研究が始まったばかりで、現象論的な解析しかできない状況でした。分子レベルでの知識を利用してシステムレベルでの解析が行えるようになってきたのは、きわめて最近のことです。ヒトゲノムプロジェクトに代表されるようなDNA配列解析などによる膨大なデータを利用することによって、ようやく我々は生物を真にシステムレベルで理解できる段階にきたのです。
それでは、「システムレベルでの理解」とは何でしょう?遺伝子やタンパク質といった分子に着目して研究を進めている分子生物学と異なり、システムバイオロジーではこれら分子で構成されるシステムに注目して研究を行っています。システム自体は物質で構成されていますが、その本質はシステムが起こす振る舞いにあり、それは単にシステムの構成要素を列挙しただけでは理解できません。同時に、ネットワークのようなシステムだけが重要だと考えるのは誤りです。システムの構成要素と両者が、システムの状態を決定するために必須の役割を担うのです。
システムバイオロジーの研究は、具体的には次の4つの大きな課題に分けられます。
- システムレベルでの理解
物理国「も含めた遺伝子制御や生化学ネットワークなどを理解する
- システムのダイナミクスの理解
定量的および定性的解析と、強力な卵ェ迫ヘを持つモデルと理論の穀z
- システムの制御方法の理解
システムを特定の状態に誘導する制御理論の穀z
- システムの設計方法の理解
特定の挙動を再現するシステムを設計できる方法の開発
生物システムの持つロバスト性などに着目した研究も活発に行われており、今後は創薬にも結びつく研究が進展すると考えられます。システムバイオロジーは、今世紀の主流を占める生物学の分野になると我々は考えています.
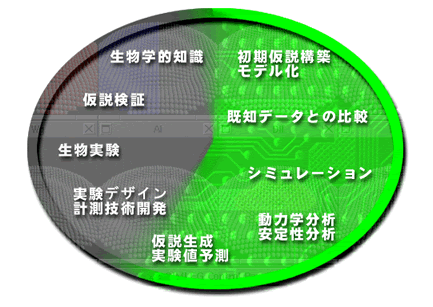
コンピュータを用いた仮想実験と従来の生物学との関係
[International
Conferences on Systems Biology]
- The 5th International
Conference on Systems Biology (ICSB 2004)
2004/10/9-13 Heidelberg, Germany
- ICSB-2003
2003/11/5 - 10, St. Louis, MO, USA
- ICSB-2002
2002/12/13 - 15, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
- ICSB-2001
2001/Nov, California Institute of Technology.
- The
First International Conference on Systems Biology (ICSB-2000)
took place
2000, November 14-16, in Tokyo, Japan.
|